「ワイの財産告白」なる名の記録を世に晒せし拙者なれど、其の源泉たる本多清六翁の名著『私の財産告白』に言及せしこと、創始の一篇を除きて未だ稀なることに、今さらながら気付き候。
ここにおいて、我が心より敬仰する日本財界の泰斗・本多清六翁の高徳と慧眼に深く頭を垂れ、併せて斯書の真価を世に広めんとの一念により、『私の財産告白』を筆の及ぶ限り要約し、布教の一助とせんと決意せり。
現代語訳:「ワイの財産告白」と題したブログを公開しているワイであるが、元ネタである本多清六氏の『私の財産告白』に触れたことが、最初期の記事以外に無いことに気づいた。今回は日本の大富豪・本多清六氏に敬意を表し、著書を布教すべく『私の財産告白』を要約してみんとてするなり。(読みやすいように2000字以内に抑えた)
『私の財産告白』要約(約1800字)
本多静六は、東大教授にして蓄財家、植林事業家としても知られる人物である。彼の著書『私の財産告白』は、学者であった自らがどのようにして無一文から財産を築き、経済的独立を達成したかを記した、いわば人生と投資の指南書である。
一、蓄財の基本は「四分の一天引き貯金」にあり
本多は給料の四分の一を必ず「天引き」して貯蓄する習慣を身につけた。どんなに給料が少なくてもこの割合を守り、残りの四分の三で生活を工夫する。貯金を「余ったらする」のではなく、「先に貯めて、残りで暮らす」ことで、習慣的に資産が積み上がっていくと説く。
また、節約を苦行とは捉えず、「節約は創意工夫の知恵であり、美徳である」と述べる。無駄を省き、知恵と忍耐で生活の質を落とさずに支出を抑えることが、人生の根幹となる力を養うという。
二、貯めた金は「自己投資」か「好景気時の投資」に用いよ
蓄えた金を単に寝かせておくのではなく、自己の能力を高めるための学問や人脈、経験への投資、あるいは不動産や株式などへの投資に用いた。特に本多は「景気が悪いときにこそ買え」という逆張りの姿勢を貫いた。
土地に関しては、地味だが確実な価値を持ち、長期で見ると裏切らない資産だと信じ、地方の不動産に注目した。地価の暴落時をチャンスととらえ、恐れずに購入する胆力が必要だと語る。
三、職業に徹し、「生活の安定と信用」を得よ
本多は「職業こそ最大の資本である」とし、安定した本業の継続が信用と収入をもたらすと説く。副業を否定はしないが、あくまで本業に忠実であることが、長期的に見て最も大きな財を築く道だと考えた。
彼は大学教授という安定職を持ちながらも、その収入を超えて蓄財を成し遂げたのは、「堅実に働き、計画的に貯め、賢く使う」という一貫した生き方の結果である。
四、心の余裕と人のために使う金こそ真の富
晩年の本多は、自らの蓄えを惜しげなく社会に還元する。自分のために使うだけの財産など高が知れており、真に価値ある金の使い道は「人のため」であると断言する。
寄付や公共への貢献を通じて、社会に役立つ「生きた金」として使うことこそ、蓄財の最終目的だと本多は説く。彼は財産の大半を寄付し、死後もその志は人々に影響を与え続けている。
五、人生の早期に「決意と実行」を
人生の早い段階で蓄財・投資の方針を固め、それを継続することが重要であると本多は強調する。「金ができたら始めよう」ではなく、「今すぐ始めよ」という精神が貫かれている。
若いころから時間を味方につけ、小さな努力を積み重ねることで、誰でも経済的独立を達成できるというのが本多の実体験であり信念である。
結び
『私の財産告白』は、単なる金儲けのノウハウではなく、「いかに生きるか」「いかに働き、蓄え、使うか」を問う人生の哲学書でもある。勤勉・倹約・投資・社会貢献という四本柱は、時代を超えて普遍の価値を持ち、現代人にも大きな示唆を与える。
本多は学問と蓄財の道を両立し、最終的には「清貧」ならぬ「清富(せいふ)」を実現した。すなわち、心も金も豊かである人生──それこそが本多清六の目指した境地であった。
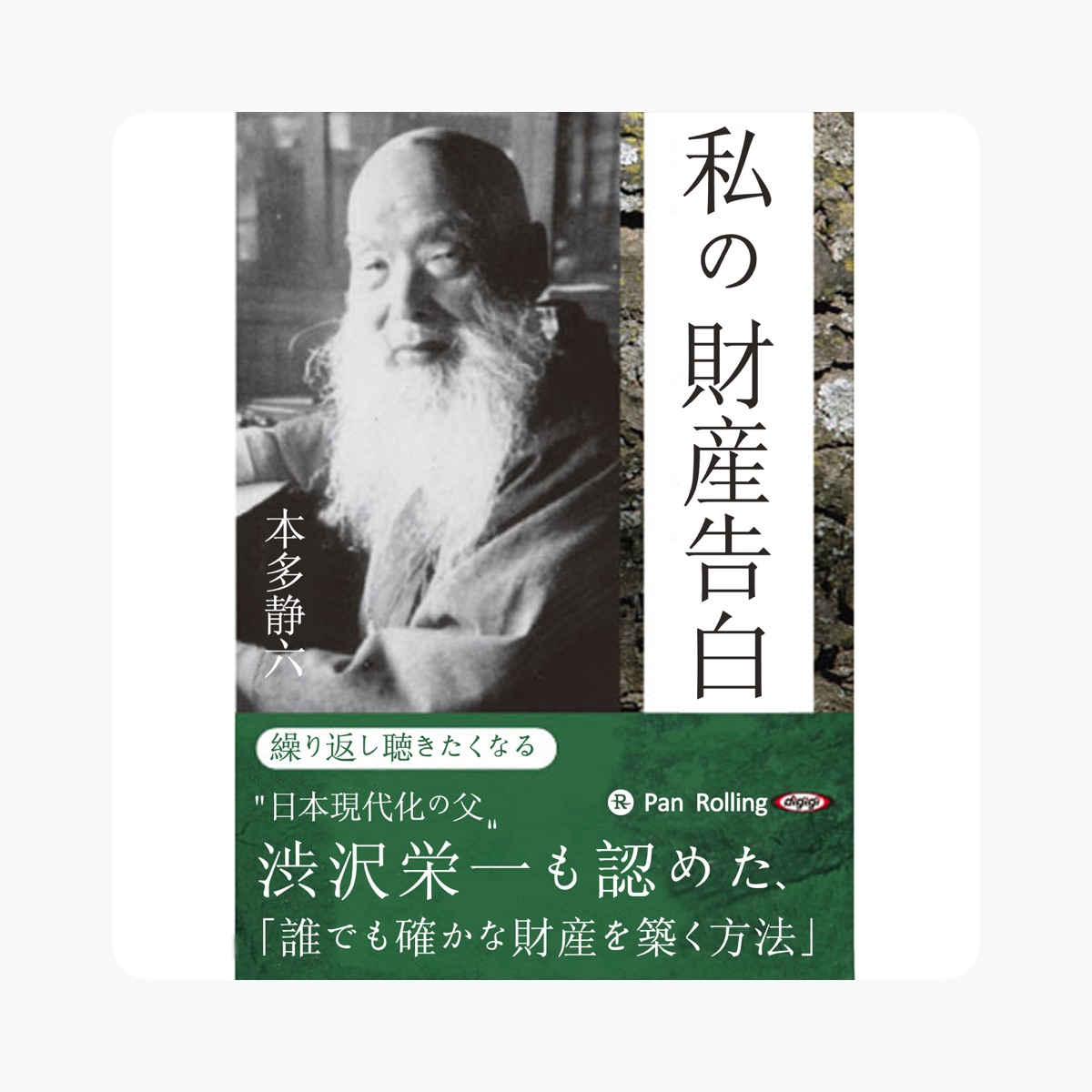


コメント